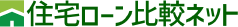住宅ローンを借りる際には、金利にばかりに注目しがちですが実はそれ以外にも必要な諸経費があります。
一般的に、新築物件であれば物件価格の3~7%、中古物件であれば物件価格の6~10%が必要と言われています。
土地建物の価格とは別にかかってくる費用になりますので、頭金や手付金とは別に現金で用意する必要があることに注意が必要です。
目次
住宅ローンに必要な諸費用の詳細
住宅ローンに必要な諸費用はどんなものがあるのでしょうか。
大手銀行とネット銀行での違いにも注目ですね。
事務手数料
住宅ローンを借り入れる際に支払う事務手数料です。
大手銀行であればだいたい33,000円(税込)、ネット銀行では借入額の2.20%(税込)が一般的となっています。
借入額の2.20%(税込)はどのくらいの金額になるのでしょうか?
| 借入れ額 | 事務手数料(税込) |
|---|---|
| 2,000万円 | 440,000円 |
| 3,000万円 | 660,000円 |
| 4,000万円 | 880,000円 |
| 5,000万円 | 1,100,000円 |
事務手数料は圧倒的に大手銀行のほうが安いですが、大切なのはトータルコストです。
印紙代
住宅購入時の売買契約書、ローンを組む際の金銭消費賃貸契約書に貼付するものです。
印紙代は住宅ローンの借入額により異なります。
借入額が1,000万円~5,000万円では20,000円、5,000万円~1億円では60,000円必要になります。
しかし、住宅ローンの契約をインターネットで済まし、紙の書類を使用しない場合にはこの印紙代は必要になりません。
それほど大きな金額ではありませんが、余計な出費がかからないネット銀行のメリットの1つですね。
登録免許税
所有権の保存、移転登記、住宅ローン借り入れによる抵当権の設定等で不動産の権利を確定する際に必要になります。
各項目ごとに税率が設定されているので住宅の購入価格により費用が異なりますが、通常は借入額の0.4%を税金として納める必要があります。
保証料
住宅ローンを組む際、契約者のローンの支払いが滞った場合の保険として専門の保証会社に保証料を支払います。保証料は借入額と返済期間を元に計算されます。
大手銀行では一括前払い型と利息組込み型があり、それぞれ額は違います。対してネット銀行では保証料は0円が普通です。
保証料は返還される
住宅ローンを借りる際に一括前支払いで保証料を納めた場合には、借り換え時や繰上返済によって返済期間が短縮された時には返還されます。しかし、返還される保証料はそれほど多くはありません。
返還金額の計算方法は金融機関や保証会社によってことなりますが、一般的に、返済を始めて5年であれば50%程度、10年であれば多くて30%程度です。この計算方法は、住宅ローンの契約書の「繰上返済・一括返済の場合の保証料の返戻についての契約条項」に説明がありますが、契約時に金融機関から説明されないことが多いようです。契約時には確認しておきましょう。
団信(団体信用生命保険料)の保険料
債務者が死亡または重い障害を患い、返済不能になった際に以後の返済が免除される保険です。
銀行で住宅ローンを借り入れる場合には強制加入ですが、住宅院友支援機構と金融機関が共同で提供する「フラット35」は加入の必要がありません。
無料の疾病保障が付帯するネット銀行の住宅ローン
団信の保険料は大手銀行でもネット銀行でも無料の銀行が多いですね。
ただし、最近ではこの団信に加えて「疾病保障」まで無料で付帯するネット銀行の住宅ローンが注目を集めています。
がんに特化したがん保障や、病気やけがまで対応した疾病保障も金利上乗せなしの無料で付帯する手厚い保障のネット銀行の住宅ローンであれば、保険料の節約にもなりますね。
無料の疾病保障付き住宅ローンを比較したこちらの記事もご覧ください。
>>無料の疾病保障付き住宅ローンを比較してみよう
各種保険の保険料
火災保険、地震保険等万一の災害に備えて加入する保険。万一の災害で住宅ローンが払えなくなった場合の保険にもなるので加入しておく必要があります。
お住いの地域により保険料が異なります。
住宅ローンの諸費用のまとめ
上記の他にも、引越し費用、新居の家具・家電などの費用がかかります。
ネット銀行は保証料は0円ですが事務手数料が必要になりますし、大手銀行は事務手数料は数万円で済みますが保証料が必要になります。
それぞれの個別の金額で比較するのではなく、金利に加えて諸費用を含めたトータルコストで比較することが大切です。
そして忘れては行けないのが、頭金や手付金とは別に現金で用意する必要があることを覚えておきましょう。
さらにネット銀行の無料で付帯する「疾病保障」は、通常であれば金利上乗せが必要になる保障が無料で付帯することで金銭的にはお得ですし、いざという時の保障が手厚いこともメリットと言えます。
![]()
住宅ローンは金利だけでなく、上記の諸費用を考え総合的に考える必要がある